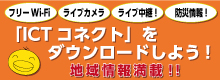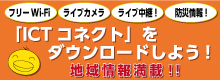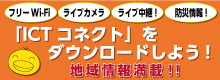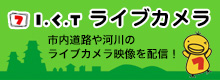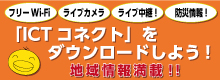ここから本文です。
巻の四十四 歴史小説についての雑感
三重大学人文学部准教授(三重大学国際忍者研究センター担当教員)高尾善希
もう読まれないのか歴史小説
私は、子どものころから、本屋めぐりを趣味にしてきました。日常で厭なことがあったとしても、とにかく、本屋におれば、それでよくて、本屋の通路で寝泊まりできれば、どれだけよかろう、とさえ思う人間です。
本屋も販売数・敷地面積の大小はさまざまですが、子どものころから観測してきた私の目からすれば、本屋も、だいぶ様変わりしたようにみえます。もっとも変わったのは書棚における面陳の多さです。面陳とは、本の表紙を表にして、立ててディスプレイすることをいいます。これだと、書棚に本を多く詰め込めないわけですが、本自体が売れなくなったので、売れ筋の本を選んで面陳するのです。その反面、書棚にある本の数は少なくなりました。また、時代小説が少なくなりました。昔は、海音寺潮五郎・山岡荘八・吉川英治などの時代小説作家の作品がずらりと多く並んでいましたけれども、最近は、あまり見かけなくなりました(しかし、例外として、司馬遼太郎・池波正太郎・山本周五郎などは根強い人気です)。山岡荘八『徳川家康』(講談社文庫)は、なんと全26巻、私は中学生時代に通読しました。しかし、こんな読むのに骨の折れる長編は、いまどき流行らないのではないかと思います。そのかわり、その漫画版が並んでいます。
司馬遼太郎・忍者・武将
司馬遼太郎は、現在でも根強い人気があります。若いひとでも、歴史の好きなひとは、よく読んでいるのではないでしょうか。司馬は、特に、高度経済成長期やそれ以降、『梟の城』(新潮文庫)をはじめとする忍者小説でも有名ですが、主に、史論風小説で一世を風靡しました。私は司馬の小説をほとんど読んでいます(小学生以来読んでいるのでかなりの冊数です)。彼が新聞記者であったので、小説上の忍者の姿に、新聞記者像を重ね合わせたようで、彼自身、忍者小説に思い入れもあったようですが、私は、彼の忍者小説の熱心な読者ではありませんでした。私が忍者ブーム以降の1974年の生まれである、というせいもあるのかもしれません。昔の読者は司馬の忍者小説を熱心に読んだのかもしれません。
最近、大学院生と一緒に、司馬の『覇王の家』(新潮文庫)を読んでみました。これは徳川家康の生涯を描いた作品です。私にとっては、前回読んだのは、高等学校時代で、なつかしく思いました。司馬の史論風小説の特徴として、大風呂敷をひろげて、読者をわかったような気分にさせる、ということがあります。たとえば、この小説では、徳川家康の生涯を描くといっておきながら、商人風の尾張者と農民風の三河者の気風の違いを論じたうえで、「三河者に推戴された家康が天下をとったことで、三河者の農民的な気風が、その後の日本の政治風土におおきな影響を与えた」ということが、裏テーマとなっています(司馬は、おそらく、家康の生涯というよりも、むしろ、こちらの方を言いたかったのかもしれません)。……現在では(そんな馬鹿な)と思いましたが、高等学校時代では、(ホウ、そんなもんかな)と思うだけで、さほどの違和感はもたなかったと思います。雑なのだけれども、1960年代、よくわからない日本人論が流行ったことからもわかるように、このような俗で大きな物語に吸い寄せられる時代であった、ということでしょう。「司馬史観」などと称揚されますけれども、眉につばして読む必要があります。けれども、その大風呂敷の文章がうまくて、魅力もありますし、一部分、しっかりとした史料を引いて、もっともな指摘もあるのがやっかいなところです。評価の難しい作家です。
ちなみに、伊賀地域には、司馬が伊賀国の旧領主である藤堂高虎を謀略家で陰険なひとのように描くので(前述の『覇王の家』にも「詐欺漢」と表現するくだりがあります)、それに不快感を抱くひとが多いようです。私も、三重大学の教員として(?)、高虎を悪く思いませんけれども、まあ、司馬は爽やかにみえる人間が好きですから、仕方がないのかもしれませんね。