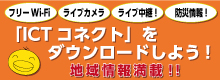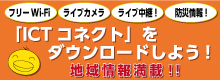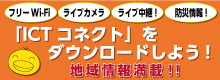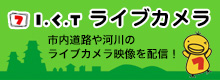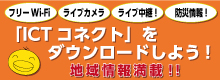ここから本文です。
巻の四十八 伊賀地域観光の現在とこれから(最終回)
三重大学人文学部准教授(三重大学国際忍者研究センター担当教員)高尾善希
うつくしい伊賀盆地
はやいもので、4年間にもわたって続いてきた本稿も、いよいよ紙幅が尽きようとしております。三重大学国際忍者研究センター伊賀研究室をお預かりしまして、7年もの歳月がすぎました。最後に、伊賀地域に勤務してきたうえでの、伊賀地域観光に関する所感をすこしだけまとめて、本稿を閉じたい、と思います。
本稿の冒頭でお話ししましたように、私は千葉県千葉市に生まれました(巻の一・巻の二)。伊賀地域の方々からすれば、ちょっと想像できないかもしれませんが、千葉県というのは、鋸山(のこぎりやま)という、素朴な名前の小さな岩山以外、山といえる山がありません。これは千葉県人の可愛らしいコンプレックスかもしれません。この地域で「ヤマ」といえば、隆起していない林のことをさしております。ですから、山に囲まれた伊賀盆地の風景は、たとえば、晴れた青い空に四方の稜線が縁どられた風景などが、私の目には、とてもうつくしく、おもしろく感じられます。早春など、霧がたって周囲が乳白色に染まるようすは、謎めいた惣国一揆の地域を連想させる風景のように思えます。これらなどは、間違いなく、貴重な観光資源でありましょう。
忍者は人気か?
「忍者は人気である」というのは、私が出席するさまざまな会議体でもいわれております。たしかに、海外の方々にしてみれば、日本というのは、たとえステレオタイプといわれようとも、ゲイシャ・フジヤマ・サムライ・ニンジャが、共通言語となっていることは、厳然たる事実でしょう。多くの忍者を発生させた伊賀地域にとっては、観光の観点から、この状況は有利なことなのかもしれません。
しかし、その一方で、伊賀地域全体が、所謂「忍者の里」であることについて、「誇りに思っている」とか、「よろこんでいる」とか、そういい切っていいかどうかは、疑問だろうと思います。松尾芭蕉と異なり、戦場で働く忍者の印象が、物騒だとか、おしゃれではないとか、そのような意見も、―私の見聞した限り―、根強くあるように思えます。忍者学を担当している私からすれば、そうであるからこそ、そのような声を無視してはいけないと感じます。
いままでとは異なる価値観を
その観点から、忍者というコンテンツを、今後はどのように育てていけばよいか、考える必要があります。伊賀地域には、必ずしも史実に基づかない忍者に関する、「売らんかな」という宣伝を、散見するのも事実でしょう(そのようなことをしなくても、伊賀地域には確かな史料がたくさんあります)。それがステレオタイプに繰り返されることも、前述の、忍者に対するマイナスの印象にも繋がっている、と思います。たとえば、60年前の提言にも、このような文章がみえます。「忍術といっても一部の観光PRだけで、そんなけったいなもの見に来よる人なんてそういるわけではない、……私が“忍術”の町でみたものは、忍者ではなく、どうやら日本のまずしい生活の素顔だったようだ。」(『忍法 現代人はなぜ忍者にあこがれるか』三一新書、1964)。
しかしながら、忍者というのは、さまざまな顔をもっております。三重大学が研究している忍者には、戦闘員というだけではなくて、豊かな知識人・科学者である、という側面もありましょう。忍術書にはさまざまなことが書いてあるからです。いままでの忍者像が、ほんとうに正しいのか、再検討の余地があります。あるいは、あたらしい忍者像を作り出していくには、どうしたらよいのか、大学だけではなくて、地域も共に、知恵を出していかなければならないところでしょう。
謝辞
長い間にわたって、ご高覧をいただき、感謝を申し上げます。編集の方から、本稿を楽しみにしていただいている読者の方が多かった由、お聞きしました。これにて本稿は閉じますけれども、私の三重大学国際忍者研究センター伊賀研究室における勤務は続きますから、今後とも、おつきあいのほどをお願いいたします。むろん、まだ言い足りないこともありますけれども、あまりに粗末ですから、おそらくここらで擱筆するのがよろしいでしょう。